
穴あけちゃった!
「小学生になろう」は、何年か前のアップルコンピュータの名コピー。
どうやら、かの毛沢東も似たようなことを言ったらしいが、理屈ではなく、素直に「いいなぁ」と思えるキャッチフレーズのひとつである。「いくつになっても、新しいことを始めるのは楽しいよね」という大人たちへの鼓舞が、簡潔に伝わってくる。
そんなわたしも、遅まきながら、2年前に小学生になった。
え?なぁになに、どこの小学校ですって?実は「耳に穴あけ小学校」なんです。げげっ、今頃?!
そう。恥ずかしながら、穴があいてから、たったの2年。まだまだ口ばしの黄色い低学年。
最初に耳に穴をあけたい!と思ったのは、いまを遡る幼稚園入園以前のこと。母の実家でテレビの「野生の王国」かなにか、みんなでアフリカ取材番組を見ていたときのこと。あまりの耳飾りの美しさに「大きくなったらゼッタイに耳に穴あけるもん!」と宣言したわたしの言葉を「女の子は体に穴あけてはダメよ」と遮ったのは、ワニ使いのおばあちゃん(当コラム・第4話参照)であった。「どうして?」と尋ねるわたしに、あたりまえのように返ってきた答えは、「皇太子妃になれなくなるでしょ!」
そもそも、そんな展開、世の中がひっくり返っても、あるわけないじゃん!どうでもいいじゃん!以外のなにものでもない。まさにムチャ振りな話なのである。その会話を聞きながら、母や伯母たちがニコニコうなずいていたことも、当時のわたしには???でしかなかった。
にもかかわらず、ある種の説得力を持ったフレーズのように聞こえたのだろう。「体に穴をあけてはならない」は、けして侵してはいけないオキテのように、心に重く、深く、刻まれたのだった。
そのひと言が心理的ハードルになったのか、わたしの耳を飾っていたのは、ずっと、ずっとイヤリングだった。ただ、イヤリングはピアスと比べて落としやすい。気にいったデザインに出会ったときには、必ず2セットずつ購入して、なんとか糊口を、いや、もとい、耳穴を凌いできた。
スポーツするとき、わたしの耳たぶはいつでもハダカ。ゴールドのピアスをキラリと光らせながら疾走するマラソンランナーの勇姿にどんなに心魅かれたとしても、スポーツジムのスパでダイヤのピアスをピカリと光らせながら、シャワーを浴びる女性タレントの艶姿にどんなに憧れたとしても、それはそれ。
けっして、じぶんごとにはならなかった。
本気で、ピアスの穴をあけよう!と決意したのは、6年ほど前のこと。
おばあちゃんはすでになく、皇太子さまは皇太子さまでご自分の道をしっかりと歩まれ、わたしはといえば、ニューヨークで流行っているクールなadidasスタイルの虜になって、カジュアルなファッションを追求するには、シンプルなピアスが必須アイテムだ!ということに、遅まきながら気づいたのだ。
しかし、決心したからといって、ものごとはなかなかスムーズには運ばないもの。
20代の友人に教えてもらって恐る恐るドアをノックした、渋谷のピアス専門医院では…。
ナース「お客様が穴をあけたい場所に、そこの黒いマジックで印つけてもらえます?」
わたし「ここらへんがいいと思うんですけど、おかしくないですかね?」
ナ「それはお客様のご責任で。こちらからは申し上げられませんね」
わ「穴あけるとき、大きな音がするんですって?」
ナ「感じ方はお客様それぞれですから、こちらからはなんとも申し上げられませんね」
という、噛みあわないやりとりのすえ、医療用ピアッサーに耳たぶを挟まれる寸前に
わ「わたし、今日こそゼッタイに穴をあけるぞって決心して来たんですけど、やっぱり今日はやめときます!」と叫んで、穴あけをキャンセル。お金を払って、逃げるように外に飛び出した。
ここまで引っ張ったのだ。一期一会の「穴あけ」は、一点の悔いなく行いたい。
しまいには、ピアス美人と見るや「どこであけたの?」と尋ねるのが癖になっていた。しかし、返ってくるのは「中学生の頃、じぶんで。氷で冷やして」とかいう、自然体で、等身大な答えばっかり。
結局、その道のプロである、某化粧品会社の広報をつとめる友人に、プロの立場でのアドバイスを求めることにした。彼女のおすすめは、テレビでもよく見かけるドクターなんとかのいる、超セレブなクリニック。もはや、お金なんかいくらかかってもいい!という心境である。
結局、表参道に面したクリニックの自然光あふれる個室で、ドクターとアフタヌーンティーを飲みかわしながら、クッキーをひと齧りするあいだに、フランス製(想像)のピアッサーがカシャン!と小さな音を立て、優雅に「穴あけ」を終えたのであった。穴の位置も、ドクターと手鏡を凝視しながら、細かく相談したので、1ミリ単位で納得のうえである。耳に印をつけたのは油性のマジックではなくて、裁縫用のチャコをデコラティブにしたみたいなペンシル。左右の位置も、顔に合わせて微妙に違うという芸の細かさ。付け加えれば、支払いもごくあたりまえの金額であった。
ここまでの一部始終を見守っていたわがムスメはひと言…
「ママ、ピアスっていうのはね。東京に出てきた女の子が、東京に慣れるためにあけるものなのよ。ママはどうして、そのときあけなかったの?どうしていま頃、大騒ぎしてるの?」
と、あきれたように、口にした。
だって、おばあちゃんが…。だって、皇太子が…。とは、わたしは言わなかった。
そう、遅れてきた小学生は、言い訳なんか口にしないのである。
その翌週、友人たちとランチをした。イヤリング派の女子4人。学生時代からの、長い、遠慮のないつきあいである。
「穴あけちゃった!」と得意げに髪をかきあげながら、ファーストピアスをみせびらかすわたし。
その耳を突き刺したのは「あちゃーっ!有理ちゃん、皇太子妃になれないじゃない!」という3人の、容赦のない叱責の声であった。
もはや、意味も理由もないのだった。まちがいない。ツーといえばカー。穴といえば皇太子。このフレーズは、清く正しく美しい、昭和の都市伝説なのだ。
女の子にとって、おばあちゃん(おそらくみんな、話の出どころは似たようなところだろう)のおまじないの言葉は、いまになっても、いくつになっても、絶対なのである。

『ER』に追いついた!
とうとう、追いついた。お尻が、見えた。
『ER―緊急救命室』。ご存知、老舗のアメリカン医療ドラマのタイトルである。
NBCの放送開始が1993年。以来1~2年遅れのペースでNHKで放映され、15年目にして、ただいまファイナル・シーズンのオンエア中。本国に遅れること丸2年。NHKでの最終放映日は3月10日あたりになりそうである。
わたしがこのドラマにはまったのは、ちょうど3年前のこと。アメリカ人に12年遅れての参入。交換日記さながら、ツタヤのDVD郵送サービスを利用して、ファーストシーズンの第1話から途切れることなくコツコツと見つづけて、ついに、レンタル解禁されている14シーズンまでの全309話すべてのストーリーを見終えたところである。
あとは、自宅のTVで録画した15シーズンを見てオンエアに追いつけば、多くの日本のERファンと一緒に最終回のフィニッシュ・ラインを越えることができる。
とうとうここまで…。1話もおろそかにせず、ネタばれを怖れて誰とも熱く語り合うことをせず、孤独なマラソンを完走……。「感慨無量」とは、きっとこの気持ちをいうのだろう。
印象的なテーマミュージックは、90年代のいつかの深夜、テレビから流れてくるのを耳にしたような気もするが、ドラマそのものを見た記憶はない。そもそも1990年代半ばは、子育てと仕事のピークが重なって、ドラマを見る余裕がなかった。当時の大ヒットドラマだといわれる、『古畑任三郎』も、『愛していると言ってくれ』も、『ロングバケーション』も、 どれもわたしは見ていない。
何周分もの周回遅れになってしまったが、こんなに没頭できるドラマに出会えたことは幸せだ。家族からは、わたしが遠くの出張からでも歯をくいしばって帰宅するのは、ツタヤから『ER』が届いてるからじゃないの?と、陰口を叩かれていたような気もするが…。打ち明ければ、『ER』さえ見られれば他に何もいらない!と何度か思ったことを、いまここで告白したい。
好きなキャラクターは、初期なら、当然ロス、スーザン、キャロル。受付のジェリー。後期なら、まさかのモリス。登場人物がみなそれぞれにダメ人間なところが、わが身につまされてたまらなくいい。
3年前、母が病気になったとき、「近所の病院ではわからなくて。あした大きな病院で再検査するんだけど……」と、見せられた血液データに目を走らせた瞬間、病名の可能性を正確に推測することができたのは、第2シーズンのスーザンが、その病気の患者を診ていたシーンを思い出したからだった。(早期治療が奏功して完治。)
2年前に、父が救急車で本物のERに運ばれたとき、慌てず騒がず当日のER担当医であった若き外科ドクターに「先生は、今日のこの手術のポイントはどこだと考えますか?」と質問し、ポイント1から3までを明確に説明できることを確認してから、「よくわかりました。先生を信頼してます。がんばって」と、力強いアメリカ人さながらの握手で彼を手術室に送り出すことができたのも、あきらかにドラマの方の『ER』で、その手術に対する基礎知識があったからだった。(M先生、ありがとう。)
「TVドラマを見たくらいで、医療知識が身についたと勘違いするくらいに、視聴者はおバカさんである」という意見も、一方にあるだろう。
だが、知識はないより、あった方がいい。考証の行きとどいたドラマから得られる知識や医療に対するセンスは、わたしたち素人を助けてくれる。
『ER』で基礎知識を身につけたわたしは、それをベースにして、母や父の通院に付き添う前夜は、専門書を調べあげて、明日の検査で発覚する可能性のある事態を予習してから、担当医と顔を合わせるようにした。それをするのとしないのとでは、当日の患者側の対処の仕方に差が出るのだ。
予備知識があれば、素人のわたしたちもオタオタしないで、治療についての建設的な話し合いに参加することができる。家族と医療従事者との間の、いい関係をつくることができる。それを治療成果に結びつけることができる……。
とかく、お医者さまは忙しい。知識のない人への説明に慣れているわけでもない。そんな医療現場では、会話のベースになる基礎単語をこちらがきちんと身につけておかなければ、専門的な知識についてコミュニケーションすることは不可能に近い。単語がわからなければ、外国語のリスニングがチンプンカンプンなのと同じことである。
そんな患者サイドの基礎トレーニングのためにも、『ER』は最適。
これから先、自分自身や家族が病気にならないという、絶対的な自信があるのなら話は別です。でも、そうでない方はぜひ、ご覧になってください。ツタヤならパソコンから申し込んだ翌日には、お宅のポストにDVDが届きます。
そういえば、キッザニアで大腸内視鏡手術のプログラムを体験したことのあるわが娘は、あるドキュメンタリー番組で「神の手」と呼ばれる名医が内視鏡手術をするシーンを見ながら「この先生、わりと上手ね。わたしもおなじ手術したことあるからわかるけど」と、のたまわった。
ひょっとしたらわたしも、おなじ穴のムジナなのかしらん?
とまれ、3月10日が、おそらく本邦『ER』の最終回。
日本中のファンと同じ瞬間、同時代人の立場で、15年分の美しいゴールインを果たしたいと思っている。

ノン-ノンストップ新幹線。
折からの米粉ブームが関係しているのか、いないのか。この1~2年、“お米の国”新潟での仕事が増えている。帰りの時間はなりゆき次第。泊まりになることも多い。しかし、行きの9時12分発「2階建Maxとき」だけは、はずせない。上越新幹線の上り&下りともに毎日1本ずつしかない、貴重なノンストップ新幹線なのである。
この直行便、東京を出ると、終点新潟まで止まらない。車内放送がない。車内販売もない。いつも座るのは、1階の自由席。この半地下車両は、出発と同時に一斉に暗くなる。勝手を知ったほとんどの乗客が、思い思いに窓の日除けを下ろして爆睡体制に入るからである。終点まで、しわぶきひとつ聞こえず、いびきだけが車内に響きわたる、なんとも快適かつ効率的な、出張エクスプレスに変身するのである。
年末のあの日も、その電車に乗るはずだった。ひと便遅らせてもミーティングにはなんとか間に合うが、できるだけ爆睡環境の整った直行便で行きたい。なにしろ、前日は深夜まで編集があって、ベッドにもぐりこんだのは明け方の4時過ぎだったのだから。
しかし、恐れていたことが起きてしまった。朝、目覚めて時計を見ると、8時50分である。家族に起こされたような記憶があるが、いまはもう誰もいない。当然、東京駅10分の徒歩圏内に住んでいるわけもなく、いつもの直行便を想定して待ってくれているであろうお得意先にお詫びの電話を掛けながら、飲まず食わずで東京駅に向かう。駅のコンコースを全力疾走して、なんとか1時間遅れの新幹線に間に合った。もちろん直行便ではない。出発ベルを聴きながら、1階3人掛け自由席の窓側の席によろよろとたどり着く。電車が動き出しても、この新幹線の日除けは下りない。車内が静まりかえることもない。がっかりしなかったと言えばウソになるが、爆睡列車に乗り遅れた以上、仕方のないことである。
窓の横にコートを掛けようとしてふと見ると、なぜかポケットが膨らんでいる。そうだ。家を出るときに、みかんをひとつ、ポケットに忍ばせてきたのだった。朝食抜きの飢餓状態を恐れる、人間の本能というものだろう。ありがとう!1時間前のワタシ。さっそく、喉の渇きを癒すことにする。
と、そのとき、いっこ置いて隣の席に、黒とグレーを基調にしたスーツとパンプスに身を固めたアラサー女子が、息を切らせながら滑りこんできた。重そうな黒いオールレザーのビジネスバッグを真ん中の席にズドンと置いた。ピカピカに磨かれていて、キズひとつない。
みかんのオヘソに親指で穴をあけながら、チラッと横目でアラサーを見ると、手持ちの書類らしきものを、背筋を伸ばして、すでに熟読し始めている。
甘い香りのするみかんの皮をゆっくりと剥きながら、わたしは、次第におかしな思いつきに囚われ始めた。
大学時代は年に3回、開通した東北新幹線で福島駅まで帰省した。当時、あきらかに「みかん」というアイテムは、車内で袖すり合った人間同士が「どちらまでですか」とかなんとか言って、相手を油断させたり、会話のきっかけをつくるためのコミュニケーション・ツールであった。誰もが車内販売を心待ちにして、われ先に「冷凍みかん」を仕入れたものである。「結構っす。喉乾いていないっす」などと言って、みかんを断る人を見たことはなかったし、断られている人を見たこともない。
さて、そのときわたしが囚われた妄想とは、こういうことである。
もし、20数年前にあたりまえにしていたように、たとえば、いまわたしが、この「Maxとき」の車内で、隣のアラサーの肩をポンッと叩いて、おもむろに、ガバッとまんなかから2つに割ったみかんの半分を、差し出したりでもしてみろ。
ネコ科の目でキッとにらまれ、同性ストーカー扱いされながら、「あっち向いてホイ!」的なプイッを喰らわされてしまうだろう。彼女がスイッと席を立ち、重いレザーバッグとともに隣の車両に移動することも、かなりの確率で確実である。
この20数年、テクノロジーの様相は激変した。もちろん、価値観やパラダイムの革命的変化は、いつの世にも存在したし、進化大好きなわたしにしても、来年の今頃はきっと、クラウドくらいは使いこなしているに違いない。でも、でも、なのである。
……みかんよ、おまえはそれでいいのか。見ず知らずの人間同士のコミュニケーション戦のリーサル・ウェポン(最終兵器)としての、輝かしい地位をカンタンに捨てて、そこらへんによくある果物になりさがってしまって、それでいいのか。
気絶しそうに眠い。おまけに、考えなければならないことはたくさんある。なのに、越後平野をゆるやかに疾走するノン-ノンストップ新幹線のなかで、暮れも押し詰まったその朝、このようなショウモナイ夢想に、わたしは囚われつづけていたのだった。

耳はイヤ~!で、目はアイズ。
子どもの頃、父が男子高校の先生をしていたので、わが家にはたくさんの「お兄ちゃん」たちが週末のたびに遊びにきた。なかでもHくんは、わたしが小学生だった頃の仲よしのひとりで、初めてキラキラと宝石のように光るフルートに触らせてくれたのも、まだ知らぬ英語の手ほどきをしてくれたのも、Hくんだった。とはいえ、Hくんの英語の授業は、「耳をつねると、イヤ~!っていうから、耳はイヤー!」だとか、「人に秘密を伝えるときは、目配せして合図するから、目はアイズ!」といった下手な落語みたいな内容だった。そんなやり取りを聞きながら、父はいつも笑って「娘にそんなでたらめ英語を教えるなら、君のことを出入り禁止にするぞ」と脅したものだ。
Hくんは、高校を卒業すると、大学生になり、高校の先生になり、結婚して、父親になり、教頭先生になり、校長先生になった。定年退職をしたいまでも、非常勤の先生として母校で教鞭をとっている。変わらない悪戯っぽい笑顔も健在。なにより、例の駄洒落には、いぶし銀のような磨きがかかっている。きっと、いまどきの高校生からも、絶大な人気があるのにちがいない。
Hくんから教わったものは、じつはフルートと英語だけではない。わが家の引っ越しの日、お手伝いの人たちに「その段ボールはそこらへんに適当に置いといてください。あとで、自分で、片付けますから」と、中学生だったわたしが言うと「ゆりちゃん、あとで、自分で、はダメだよ。いま、どこに置くかをきちんと話せば、いま、片付く!」と、効率と体裁の微妙な境界線を教えてくれたのはHくん。
「仕事と子育てに完全燃焼してま~す♪」と、年賀状に書いた30代のわたしに「残念ながら女の人はそれだけでは足りません。ダンナサンをすっかり忘れてるでしょ!」と、返事をくれたのもHくん。人生のツボをさりげなく押さえてくれる、影の指南役でもあったのだ。
いまではわたしも、まわりに合わせてH先生などと呼んでいるHくんだが、数年に1度、顔を合わせる。話しているうちに、いまがいつなのか、じぶんが何才なのか、だんだんわからなくなってくる。先月、わたしの父の訃報を聞いて、駆けつけてくれたHくん。実家の居間に溢れる人垣のすきまから、何気なく目配せをすると、Hくんからも間の悪い目配せが返ってきた。数十年にわたる交友をつうじて、最もぎこちない合図になった。ふたりとも、あふれだす涙に、思いっきり邪魔をされたのである。
途方もない悲しみや苦しみのなかにも、ある種の楽しさは見つかるものだ。父もまた、そのことを知っている人間だった。
なくなる前日のこと、「ゆりちゃん」と苦しそうに自宅のベッドから名前を呼ぶので「どうしたの?脚がいたい?」と聞きながら近づくと「そうなんだ、ピンポン大当たり。脚がいたいんだ、困ったなぁ~」と言って、父は笑った。「なに笑ってるの~、こんなときに」と言って脚をさすりながら、笑っている父が可笑しくなって、わたしも笑った。
お通夜の日、Hくんに「お父さん、高所恐怖症で、高いところをあんなに怖がっていたのに、無事に天国まで昇っていけると思う?」と聞いた。すると「先生、甘えん坊だったからねぇ」という、意外な答えが返ってきた。やさしい先生でした、立派な方でした、思いやりのあるすばらしい人でした、感謝しています、先生なくしていまの自分はありません、あんなに啓発される方はいませんでした。…そんな、涙なしには聞けぬ語れぬ言葉の海のまんなかに浮かんだ「甘えん坊だったからねぇ」という、なんとも楽しげなそのひと言は、波のまにまに漂う流木のようにゆらゆら揺れて、しばらくの間、わたしの心に、下手くそなフルートが奏でる「ユーモレスク」の旋律を響かせた。

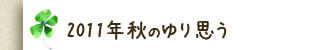
六本木、みずほ銀行(その1)。
♯30 wrote:2011/11/03
どこがクールジャパンだ (ゆりコラム番外編)
♯29 wrote:2011/10/14
たいそう温かな日曜日。
♯28 wrote:2011/10/17
グイッ!と、ファイト何発?
♯27 wrote:20111/10/10

イメージvs.イメージ。
♯26 wrote:2011/09/01
福島から風穴をあけて(ゆりコラム番外編)
♯25 wrote:2011/08/09
アーカンソーの魔女の長い爪。
♯24 wrote:2011/07/18
美肌モードの謎。
♯23 wrote:2011/07/16

プロボノ、ボンベ。
♯22 wrote:2011/06/26
何みりしーべると?のハンゲ(半夏生)。
♯21 wrote:2011/05/29
愛さずにはいられない。
♯20 wrote:2011/05/25
ソーシャル・ネットワーク、
まだなにも知らなかった。
♯19 wrote:2011/05/08
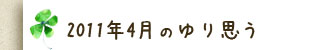
引退。
♯18 wrote:2011/04/19
逆向きのアンテナ。
♯17 wrote:2011/04/17
2011年、夏。奇跡の夜型都市、東京。
♯16 wrote:2011/04/10
故郷の町、電波時計の怪。
♯15 wrote:2011/04/04
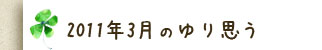
緊急対策の先にあるもの。
~ピンチをチャンスに変える、復興のビジョン~
(ゆりコラム番外編)
♯14 wrote:2011/03/24
いま、なぜ、トラベルミン?
♯13 wrote:2011/03/22
プールに水を溜める。(福島原発)
♯12 wrote:2011/03/20
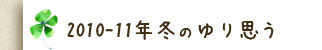
穴あけちゃった!
♯11 wrote:2011/02/22
『ER』に追いついた!
♯10 wrote:2011/01/25
ノン-ノンストップ新幹線。
♯9 wrote:2011/01/05
耳はイヤ~!で、目はアイズ。
♯8 wrote:2010/12/13

未練はない、ゴー!
♯7 wrote::2010/10/31
忘れんぼクイーン。
♯6 wrote::2010/10/24
ごめんくだシャイ。
♯5 wrote:2010/10/16
鰐とおばあちゃん。
♯4 wrote:2010/10/04
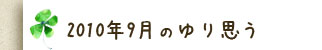
悪女の深情け。
♯3 wrote::2010/09/27
いちばん好きなコンセプト。
♯2 wrote:2010/09/21
中学生向けのコピーで、満足ですか。
♯1 wrote:2010/09/13



