
イメージvs.イメージ。
地産地消(ちさんちしょう)という、舌を噛みそうな言葉を、初めて耳にしたのはいつのことだろう。
記憶の糸をたどってみると、新潟の仕事で、取引先の食品会社の社長の言葉として聞いたのが最初だったような気がする。出張先というタイミングだったので、「なになに、新しくできたビジネスホテルですか?」などと、たぶんおっちょこちょいなわたしは聞き返したんじゃないか。(それは、チサンホテル…。)
赤面するほど耳なれない言葉であった。おそらく7~8年前のできごとである。
その地産地消が、いまでは、しっかり世の中に根づいている。
考えてみれば、地元の農産物を、地元で食べましょうよ、という考え方は、あたりまえのこと。
育てた人の顔を見たり話をしたりしながら、おいしくて安心な食材を買いたい!と願うのは、ごく自然な感情だし、なにより、旬の食材を使った、その地域の食文化に溶けこんだ料理をいただくのは、人生の幸せのひとつだろう。
生産者の側から見ても、不揃い品や規格外のものも遠慮しないで販売できるので、農業へのやりがいがふくらむし、輸送コストの減少にもつながり、CO2の排出量もその分だけ少なくなる。新鮮な作物を最安値で、いちばん環境にやさしく出荷できるというわけである。
作物の特長をうまく見つければ、スローフード運動や、町おこしの起爆剤にもなるだろう。
結果として、食料の国内自給率アップに貢献できるのだから、これはまさに、ウィンウィン。いいことづくめの運動だといえるだろう。
そういえば、千葉県のスーパーマーケットで、「千産千消」というキャッチフレーズのポスターを見たことがあった。
何やらこのダジャレには、お役所の臭いがするぞ。ひょっとしたら地産地消は、個々の地域の自然発生的な運動ではないのかも…。
そう思って調べてみると、2005年に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」で、地産地消の推進がうたわれ、昨年の12月には「六次産業化法」という、農林漁業の地産地消を推進する法律が成立していた。物知らずなわたしは知らなかったが、これはなんと、押しも押されもしない、国の政策だったのである。
とはいえ、仏教にも「身土不二(しんどふに)」という言葉があったはず。たしか、人の行動と環境は切り離せないという教えだった。そのような意味からも、地産地消は本来、人として自然で、ひじょうにメリットの多い取り組みにちがいない。
あの日がくるまでは…。
3月半ば、美しい福島の田畑の上空数十メートルを、放射能の風が吹き抜けた。
その瞬間、“地産地消”が、福島に住むひとにとって、もうひとつ別の意味を持ってしまった。
これは、先月、地元の友人から聞いた話である。
福島県内の大きな町に住む友人一家は、とりわけ彼の妻は、小さなふたりの子どもへの放射線の影響を心配していた。
ある深夜遅く、彼が仕事から帰宅すると、子どもたちはもう眠っていて、家じゅうの電気が消えた中にぽつんと座っていた妻が、「明日から子どもたちに、何を食べさせたらいいの?」といって、泣きじゃくったという。
話を聞いてみると、その日から、行きつけだった近くのスーパーで『負けるなふくしま!地元の野菜を食べよう!!地産地消フェア』と銘打つ、販促キャンペーンが始まったのだという。その日、その店の野菜売り場には、地元の野菜だけが、ところ狭しと並んでいたそうである。
「学校の校庭の放射線量を心配して、一日中窓を閉め切って、外にも出られないうちの子たちが、そのうえどうして、地元の野菜を食べろ、食べろって、いわれなきゃならないの?」
彼女のいうとおりだ。これほどの矛盾があるだろうかと、彼も泣きたい気持ちだったという。
それから数週間の話し合いを経て、奥さんと2人の子どもたちは、仕事のある彼ひとりを福島に残して、西日本のある町に引っ越して行った。
おなじような話は、福島県で人と話す機会があれば、いまなら、誰もが耳にすることだろう。
地産地消が、福島の母子を苦しめる言葉に、変貌してしまっているのである。
これは、ウィンウィンにすら見えた施策が、非常事態のなかでは一転して、生活者を傷つけてしまう事例のひとつかもしれない。
あらためて確認しておきたいのは、そのスーパーマーケットが取り扱っている野菜は当然、国の暫定基準値をクリアした安全な野菜ばかりだということである。
だから、友人の妻が泣いたのは、環境放射線量の高い町に住み、外部被曝への危険にさらされているわが子を心配する母親としての、その野菜の安全性の「イメージ」への拒否反応だっただろう。
外部被曝しているかもしれないわが子を、これ以上、内部被曝させる危険に触れさせるわけにはいかないという、母としての本能。そんな彼女の気持ちを思うと、胸がいっぱいになる。
そしてまた、「イメージ」への反応という意味では、首都圏にまん延している風評被害もおなじことである。そこに科学的裏づけはない、その感情は実に本能的で、反射的な抵抗感にすぎない。
福島の農業を復活させるために、このイメージという怪物を消し去ることさえできたら…。
しかし、ついてしまったイメージを払拭するのは、なかなかの重労働だといわざるをえない。
イメージを打ち消すことは、より強固なイメージにしかできない仕事だからである。
イメージを上書きすることができるのは、事実に裏打ちされた、より強力なイメージでしかないのだ。
先日のお盆休みに帰省したとき、実家の近くにある、近隣の町村からの野菜を商うプレハブの直販店と、隣市の駅前にある地物の野菜を扱う路面店を巡った。
どちらの店も、安全基準を満たした野菜だけを販売している。そこにあるのは、みずみずしい、穫れたての輝きを放つ野菜であった。店内は、予想をくつがえして、地元のお客さんであふれ返っている。
ここでは、あいまいな「イメージ」を、愛郷心という強固な「イメージ」が打ち消しているのだった。
しかし、この愛郷心を利用したイメージ上書き作戦は、首都圏では通用しない。
いったい、どうしたらいいのだろう…。
仮にもし、『微量の放射線は、むしろ健康を促進する。低量の放射線を浴びた野菜を食べれば、がんになりにくい』という、一部の学者の先生の説が科学的に実証でもされれば、それは、より強力なイメージづくりの力になるのだろう。
しかしながら、がんの発症についてのデータが出そろうにはおよそ60年かかるともいわれている。
科学的データの力で、現在のイメージを上書きすることは難しそうである。
ここまで考えたものの、新たな強いイメージをさがしあぐねて、わたしは途方にくれてしまう…。
考えてみれば、国の安全基準が信用ならないことが、そもそもの問題の元凶なのである。
国は信じられない、というのが、首都圏に住む生活者のいつわらざる気持ちだからだ。
この懐疑心こそが、ついてしまったネガティブイメージを消し去る足かせになっている。
ことここに至った以上は、国からも官僚からも独立した、顔の見える検査機関が必要なのではないだろうか。
独立した検査機関が真剣に検査を請け負って、「アトミック・ゼロ(放射性物質未検出)」の検印を押してから出荷するというスピーディーな体制づくりが必要である。それが、大事なときに頼りにならなかった国が、いま取れる責任ではないだろうか。
こと食の安全に関するかぎり、もう国には任せられないと思うところまで、生活者を追い詰めたのは、他でもない、国と官僚そのものなのだから。
地産地消を是としたわたしたちの気持ちのベースにあるのは、顔の見える相手に寄せる信頼である。
放射性物質ゼロを保証する方法もまた、顔の見える手法がいい。
「わたしが検査した安心な野菜です」という言葉の横に、検査した人の顔写真を添えるのはどうか。
もちろん、個人の名前も、検査機関の所在地も、しっかりと明記する。
不誠実のうえにも不誠実を繰り返してきた、国と官僚を信じられなくなっている生活者がいま信じられるのは、何一つ見逃すことなく、厳しい目線でモニタリングに取り組んでくれている検査員ひとりひとりの、誠実そうな顔写真だけなのかもしれない。
持たされてしまったイメージをくつがえす、もっと強く、もっと信頼に足る別のイメージが、いま必要とされている。

福島から風穴をあけて(ゆりコラム番外編)
この五カ月「ご実家はどう?福島は大丈夫?」と、わたしのような者までが誰かれとなく声をかけられる。「母は元気。でも県内の放射線が心配で」などと答えながら、胸が熱くなる。不安のなかに故郷を誇らしく思う気持ちが交錯する。
福島に住む人は、三・一一以来、世界の称賛を受けている。家を、愛する人を、大切なものを失ってなお、起きてしまった悲劇の前で感情を爆発させたりしない節度のある姿が「高潔な人たち!」と感嘆されている。
福島の人はガマン強く、礼節を重んじる。戊辰戦争で朝敵とされたが、以降百四十年余り、めげずに生き抜いた不屈の魂がある。自由民権運動から続く正義感と負けじ魂がある。わたしのように福島で生まれ育った「福島のシマンチュ(島人)」にも、それは既知の事柄である。
本心を言えば、原発事故などというこんなにひどいことが起きてしまったのだから、わたしはこれをきっかけに日本は何かが大きく変わるだろうと思っていた。しかし、あれから五カ月がたつのに、このパターン化した国にダイナミックな意識や規範の変化は訪れない。悲しいけれど、それが現実…。
長年、コミュニケーションの現場で仕事をしてきた立場から感じるのは、礼節や冷静さはこの際、脇に置いて、ということである。変わらない現状に、福島からもっと、もっと、ノー!を発信してほしい。それが日本人の価値観を変えることにもつながっていく。
放射線の恐怖におびえながらの生活はノー!家族離散はノー!仕事がないのはノー!除染した表土の山にブルーシートをかぶせて校庭に放置するのはノー!国の無策はノー!手塩にかけて育てた牛の出荷停止はノー!先祖代々の田畑が絶やされるのはノー!先の見えない状況はノー!
首都圏の被災地イベント等で、福島の農産物が飛ぶように売れていく光景を目の当たりにしている。風評被害とは別のところで、差しのべる手の存在を肌で感じる。もっと多くの人を巻き込みたい。猫の手でも借りまくれの精神である。それには「福島からの発信」がキーになる。言葉は自由だし、動画投稿サイトは無料だ。
いままで「福島ってどこだっけ?北陸?あ、あれは福井か」などと、普通に言われてきた。だが、いま福島は、新しい「ふるさと」のあり方を、これからの日本人の生き方を、未来のエネルギーの枠組みを、思索、構築するフィールドの中心地である。
すべてをいい方向に進めるために、スピードは必要だが、むだに焦ってほしくない。風評はいつか消えるが、地に足のついた取り組みは消せない。同情は続かないが、信頼は長く続く…。
一方で、二〇二〇年に東京五輪を招致するプランが浮上しているという。申し訳ないが、東京のでる幕ではないだろう。困難に立ち向かう福島が、遠くの山なみに目標としてかかげるともしびこそが、たとえば「二〇六〇年ふくしま五輪」であろう。子どもの世代の、孫の世代の、オリンピックだ。
「試練を乗り越えた福島は違う」「新しいふるさとのカタチをつくったね」「美しいエネルギー社会のモデルだ」と、世界中が憧れる、未来の福島…。これは、シャクナゲが匂いみどりが光る空のかなたに一人のシマンチュ(島人)が描いた、小さな夢のひとつ…。
目の前に山積みにされた大小の困難をひとつひとつ乗り越えることに精いっぱいで、先を語るなどいまはご法度かもしれない。しかし、みんなにもっと、語ってほしい。かつてない体験のさなか、福島からの発言には説得力がある。それこそが、よどんだ日本に風穴をあけるに違いない。
♯25 YURI wrote:2011/08/09(※本稿は、福島民報社のために書き下ろしました。著作権等は同社に帰属します。)
アーカンソーの魔女の長い爪。
友人が来月、NYに行くという。
夏休みを利用して、語学留学するというのである。
すると別の友人が「だったら、ここと、ここは外せない。この店のイタリアンは絶対だよ!」なんて、知恵をつけている。
わたしは、NYを舞台にしたドラマ「SATC」の大ファンだったし、再放送を何度も見ているので、背伸びをすれば話題についていけないことはないのだが、でも実はNYに行ったことがないので、ひとり、むしゃむしゃランチを食べている。
NYこそ未踏の地ではあるが、南部のミシシッピデルタ地帯、テネシー州とアーカンソー州とミシシッピ州、それにテキサス州は訪れたことがある。仕事だったけれど、約2週間、ロケバスであちこち動き回った。
これってまるで、東京には行ったことないのに、青森と岩手と秋田と宮城は訪問済みの外国人みたい?
なかなかディープなアメリカ履歴だと思うのだが、こんな例えは、ひょっとしたら、とんちんかんなのかな。
それにしても、DKNYの洋服は山ほど持っているのに、ヤンキースのキャップも被っているのに、人生なかなか思い通りには運ばないのである。
さて、わたしがアメリカ南部に行ったのは、10数年前、まだ広告代理店の社員だった頃、とあるスポンサーの1社提供で、5分枠の帯番組をつくった時のことである。内容は、アメリカの牧牛地帯巡り。あの有名な「世界の車窓から」とおなじチームが制作を担当してくれることになり、撮影前からワクワクしていた。
「成田から出発して、LAとシカゴで国内線に乗り継ぎます。メンフィス到着は深夜になりますので、その夜はメンフィスで一泊してください。翌日の正午、アヒルの行進で有名なPeabody Hotelの、アヒルのいる池のまわりでぶらぶらして待っててくだされば、だれか手のあいた奴が迎えに行きますから。そいつのピックアップトラックに乗って、撮影隊に合流してください」
前日に届いた、なんともアバウトな撮影チームからのFAXを折りたたんでパスポートケースの中にしまい、ひとり成田を旅立ったのは、寒い1月のある日のこと。
だだっぴろいシカゴのオヘア空港で、国内線の乗り換えに四苦八苦。ようやくたどりついたメンフィスの空港では、黒人の係官に「あなたの英語は訛ってて、ぜんぜん聴き取れない」と、繰り返し繰り返し発音練習をさせられた。
生まれてはじめてのアメリカ本土上陸だったのに、深夜のメンフィス空港のタクシー乗り場は、しんしんと底冷えしてくるばかり。南部の冬の大地はいかにも冷たく、こんなとこで、いったいなにしてるんだろうと、息で手のひらを温めながら、寒さと空腹で泣きそうになるわたし。どんなに待っても、タクシーなんか1台も来ないし、英語もぜんぜん通じないし…。
覚えているのは、めげてはダメだと、自分を奮い立たせながら、ようやく1台つかまえたタクシーでたどり着いた寒いホテルの一室で、猫みたいに丸くなって眠ったこと、そして翌日、約束どおり迎えにきてくれたアメリカ人スタッフのジョンと無事に会えたこと。地平線までつづく綿花畑の中を走るルート70号線をガタゴトと、ピックアップトラックを走らせながら、初対面の彼といつのまにか意気投合して、長い長い道のりを、壊れたラジオみたいに、ジョン・デンバーのCountry Roadを、何度も何度も仲よく歌ったことである。
お尻は痛くなったが、夕方、ジャクソンの町に到着。予定通り、撮影隊に合流した。
アメリカ人と日本人混合のNYからの撮影クルーは「よく来たね。ぼくたちも、この町の人の英語はぜんぜんわかんないから気を落とすな」と、迎えてくれた。
わたしが合流したタイミングは、ガソリンスタンドのチェーンを経営する町の大物が、大邸宅を使って撮影隊のために開いてくれるという歓迎パーティーが始まろうとする直前であった。ラッキーである。
気がつくと、身なりのいい白人の人たちが入れかわり立ちかわり近づいてきて「京都に行ったことがあるよ」「弟が沖縄にいたわ」などと、聴きとりのむずかしい英語で、声をかけてくれている。
そのとき、いままさにスカーレット・オハラが降りてきそうな螺旋階段の上に、ちらっと女性の白い顔が見えた。
あとでわかったのだが、彼女こそ、この大邸宅の奥さまで、ウェディングドレスのデザイナーとしても成功している女性。町の名士夫人と実業家の2足のわらじを見事に履きこなす、その町に咲き誇る花のような存在であった。
レーガン大統領のファーストレディだったナンシー夫人に似た面差し、小柄ながら、この人こそが夫を牛耳っているのだな、と思わせるデモーニッシュな雰囲気があった。
彼女が私を見降ろし指差して、何か言ったような気がしたが、わたしにはその英語が聴きとれなかった。
「いま着いたアジア人の女の子、ちょっと来て、と、いってる」と、日本人カメラマンKさんが、ぼそっと通訳してくれた。
その瞬間、わたしの上半身は、金縛りにあったように固まっていた。
まるで、奥様の長い人差し指の先がハリーポッターの魔法の杖ででもあるかのように、長い豪華な螺旋階段を、背筋をまっすぐに伸ばしたまま、彼女の自室へ向かって、ふらふらっと操られて上っていったのである。
ドアをノックすると、すぐに返事があり、中に入るとレディーは後ろを向いて立っていて、両手で髪を押さえている。
「さっさと、後ろのチャックあげて」と言われたことはわかった。
膝まづいて、白いカクテルドレスのファスナーをていねいにあげ終えると、「サンキュー、もう下に行っていいわよ」と、お礼を言われ、犬を追い払うような手つきで階下に追い払われたことも。
わずかな時間のあいだに、階下には、「風と共に去りぬ」を彷彿とさせる、ふりふりのパーティードレスを着た若い白人の女の子たちが、ぞくぞくと集まってきていた。彼女たちは、正装した男子たちと、よく食べ、よく笑い、よく踊った。
あわててトイレに行ってジーンズを脱ぎ、1枚だけ持ってきたワンピースに着替えたわたしは、これは歓迎パーティーの名を借りた、地元のねるとんパーティーなんだね、とNYから来た撮影スタッフと話しながら、本式のフライドポテトにがつがつ喰らいつき、本場のバーボンをがぶがぶ飲んだ。
2週間の撮影のあいだには、南部の町の黒人だけが行く教会の日曜礼拝に参加して、本物の聖歌隊のど迫力なゴスペルに合わせて、席を立って踊っていた人々が次々にトランスして、バタバタ倒れていくのを目の当たりにしたり、オレンジカウンティーの黒人の子どもたちと、学校の校庭でバスケットボールで半日遊び、バスケの本当のおもしろさに目覚めたり、「いまこの店がテキサスでいちばんINなんです」と評判のステーキハウスで、シェフ直伝の本場のステーキの焼き方を手取り足とり教えていただいたり、たくさんの収穫があった。
もちろん、ドキュメンタリー番組撮影のイロハも、リアルに経験させていただいた。体力的には過酷だったが、すべての瞬間が楽しく、NYからきたスタッフが連発するジョークに、腹がよじれるほど笑ってばかりいた。
若い頃の苦労は買ってでもしろというが、それは本当だと思う。あのとき「おまえが自分で立ち会いに行けよ」と算段してくれた当時の営業担当の大先輩には、いまでも心から感謝している。
でも、なにが忘れられないって、人差し指1本で、くいくいっと操られ、2階にあがり、膝まづいて、奥さまの背中のファスナーを恭しく締めた、わたしの行動の不可解さである。
人生を通して、命令をするのもされるのも、大嫌いだったはずなのに、それが何なのかよくわからないまま、否応なく操縦され、ひたすら従順に従った。
あの瞬間、彼女の白い指と、長い爪、美しく塗られたゴールドのネイル、いや、それ以上に、自分こそが支配者であることを既成の事実として一切疑おうとしない彼女の強い信念に幻惑されて、自分が自分の支配者であることをたやすくあきらめてしまった、アジア人の若い娘…。それがわたしなんだ。
自分自身の中に潜んでいた、服従する魂。支配を蹴飛ばすことなく、反射的に飼いならされてしまった弱い心。
わたしたち日本人には、支配と服従という二項対立に陥らないだけの、柔らかな東洋の知恵、または一休さんの頓知という、最強の武器があったのに…。
あの時の、無策でへなちょこだったわたしを思いだすと、悲しくなる。

美肌モードの謎。
最近ちょっと、不思議に思うことがある。
じぶんのことをこんなふうに書くのは気がさすが、銀座の大通りなんかを移動中に、ウィンドゥにうつったわたしが、やけにいい感じなのである。朝から打ち合わせ祭りで、ろくにお化粧直しもしていないのに、なんだかとっても、肌がきれい…。
疲れはてて帰宅した深夜、家に帰ってのぞきこんだ洗面所のミラーに映る顔も、かなりのダメージを覚悟しているにもかかわらず、意表をついて、予想外の美肌モード。
「ママ、ツヤツヤしてる。お酒のんできたのぉ?」とワガムスメからは疑いの目を向けられる始末。
ちがう、ちがう、一日ろくにご飯も食べてない。
子どもの頃から色黒で「七難隠せてないからねぇ…」と祖母を嘆かせてきたわたしの肌が、このところ、なぜか奇妙に色白なのである。
朝起きて覗きこんだ、トイレの鏡にうつる顔に、透明感がある。クリアネス。
一時期気にしていた両頬の肝斑も、毎朝きちんと飲んでいるトラネキサム酸のカプセルが効いているのか、いないのか、いまではほとんど気にならない。
なんだか、おかしい…。ってか、あやしい…。
いや、本来わたしって、さほど色黒ではないのかも。その証拠に、顔以外の皮膚、とくにお腹やお尻などの外気に触れないボディーは、なかなかの色白ではないか。
幼稚園入園以前のぶらり山歩き、学生時代のテニスにスキーにウインドサーフィン、最後の仕上げに子育て時代のお砂場通い…。
このような、小麦色の肌づくりへのたゆまぬ後天的な努力で、どんどん、黒キャラに染まってきただけであって、もともとの丈夫な鈍感肌が、人生後半戦に差しかかろうとしているいま頃になって、とうとう花咲こうとしているのではないかしらん?
と、強引に話をまとめてしまおうかとも思うが、やっぱり妙なものは、妙なのである。
そんなわけで、どうにもこうにも、狐につままれたような気持ちで、日々を過ごしているのだ。
先日も、まあいいや、悪いことじゃないんだし、とつぶやきながら、鏡に向かって首をかしげていると、ふと、思い出した光景がある。
それは、わたしの父がハクナイショウの手術をした翌日のことであった。
父が入院したのは、地元にある温泉つきの有名な眼科専門病院で、全室個室であった。
温泉付きか否かは、当事者にとってははっきりいってどっちでもよく、それは、つきそいの家族を喜ばせるための温泉であった。たいへん豪華な施設ではあったが、夜の看護婦さんの見回りは付き添いであっても容赦のない目配りのいき届いたもので、患者用のベッドで寝ている父はもちろん、備え付けのベッドで爆睡しているわたしの顔も、懐中電灯でぴか~っと照らして確認するのだ。このサプライズ攻撃が夜中に数度、廻ってきた。
24時間監視付きの高級ホテルだと考えていただくと、イメージがわきやすいかと思う。
そんな素敵な病院であったが、父が入院していた1週間、わたしと母が、交代でつきそうことになった。それなりの長丁場である。さて、入院3日目に手術が無事終わり、その翌日の14時、時報とともに、とうとう両目を覆っていた包帯を外す瞬間がやってきた。
お医者さま立ち合いのもと、頭の後ろの粘着テープを、看護士さんがひょいひょいとはがし、するするっと包帯をとるやいなや、予想以上のことが起きた。
「おぉ、カレンダーがはっきり見える!」
「わぁ、時計の針がよく見える!」
「なんでも見える!」
父のほがらかな声が、病室中に響きわたった。
それは、おなかの手術で、前月まで不本意な入院生活を送った父が発した、久しぶりの明るい声であった。
「看護士さんは、声からいって美人にちがいないと思っていましたが、こんなに美人だとは思わなかった!」
そんな冗談を、父が愉快な調子で口にするにおよんで、病室は、爆笑の渦に包まれた。
しかし、父の感慨は歓びばかりではなかったようである。
やがて、みんなが出て行き、病室に家族だけが残ると、父は手にした手鏡を離さずに、ためつすがめつ、しはじめたのである。
「おれってこんな顔だったのかい…」
「歳とったなぁ…」
といいながら、じぶんのお顔を、なにか珍しいものでも見入るような表情で、長時間見入っていたのであった。
わたしが思い出したのは、その時の、世にも不思議そうだった父の様子であった。
ひょっとして、もしや、わたしも、老化が目にきて、肌のアラが見えなくなっているのではないかしら…?
いやいや、だいじょうぶ、先日の運転免許更新のときも引っかからなかったし、健康診断でも、視力はまずまずだった。
でも、だからといって、肌がツルンとしたわたしなんか、わたしではない。このまま、このきれいな肌を放置しておくわけにはいかないわ。と、なんだかだんだん、意味不明…。
だれかにほんとうのところを聞いてみたいが、わたしの肌をどう思う?などという正面突破では、だれも本音で答えてはくれないだろう。
そもそも、仕事仲間の野郎どもは、こちらの肌なんかろくに見ていないだろうし、女友達は女友達で、この手の話題は正直微妙。なかなか面と向かっては聞きにくい。
思いあまって、夫にこの問いをストレートにぶつけてみたところ、
「うん。たしかにキレイ。プリプリしてる!」と、やけに愉快そうにいったので、鵜呑みにすることはできない。このような受け答えは、冗談である可能性がひじょうに高い。
われながら、悩ましい問題を抱え込んだものである。行けば天国、帰れば地獄。答えを知りたいような、知るのが怖いような、なんとも足元のおぼつかない状況。まあ、いずれ何事も、真実を知るのは、とても恐ろしいものなのであるが。
あれこれ考えるのが面倒臭くなって、もうこうなったら、知らない人に聞くことに。
なにをいっても恨みっこなしな人。二度とつながりのなさそうな人。とはいえ、いきなり工事現場で誘導灯を振ってるおにいさんにナヨッと近づいて「ねぇ、あたしって肌きれい?」では、勘違いされてしまうだろう。
ならば、少しくらいのつながりは、よしとすることにして。
わたしが白羽の矢を立てたのは、ムスメが通う塾の先生である。
ムスメによると、なにごとも歯に衣きせずに、ビシバシ指導してくれるので、学力がメキメキついてきた気がするというのである。まあ、学力についてはムスメの自己申告なのだが、なにはともあれ、信頼するこの先生にお伺いをたてるしかあるまい。
しかも、女性。しかも、年上。人生の先輩。だんだん、この方をおいてほかにはないという確信で胸はいっぱいになる。
ムスメの成績はいかがでしょうか?と尋ねにきたふりをして、そのついでに、ところでわたし、最近肌の調子が妙によくて、とくに色が急に白くなったような気がするんですけど、どういうことなんでしょう?と相談してみることにした。
ある日、クルマでムスメを迎えにいった夜のこと、成績の話を適当に切り上げると、勇気を出してわたしはその質問を口にした。
「あぁ、お母さん白いですねぇ。白人みたいにまっ白!」
目はマジである。しかし、先生の唇の端をよく見ると、震えている。まちがいない、笑いを堪えようと必死になっている。暑さのせい?またはムスメの成績の伸び悩みが心配で、アタマが熱中症になったお母さん、と思われてしまったのかもしれない。
だいたい、あやすような口調がやさしすぎる、あらまぁお母さん、落ちついて落ちついて、ドウドウ。
質問が悪すぎたか…。
そういうわけで、はっきりものをいってくれる候補ナンバーワンは、早くも玉砕。
謎はいまだに、謎のままなのであった。

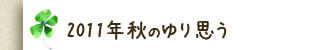
六本木、みずほ銀行(その1)。
♯30 wrote:2011/11/03
どこがクールジャパンだ (ゆりコラム番外編)
♯29 wrote:2011/10/14
たいそう温かな日曜日。
♯28 wrote:2011/10/17
グイッ!と、ファイト何発?
♯27 wrote:20111/10/10

イメージvs.イメージ。
♯26 wrote:2011/09/01
福島から風穴をあけて(ゆりコラム番外編)
♯25 wrote:2011/08/09
アーカンソーの魔女の長い爪。
♯24 wrote:2011/07/18
美肌モードの謎。
♯23 wrote:2011/07/16

プロボノ、ボンベ。
♯22 wrote:2011/06/26
何みりしーべると?のハンゲ(半夏生)。
♯21 wrote:2011/05/29
愛さずにはいられない。
♯20 wrote:2011/05/25
ソーシャル・ネットワーク、
まだなにも知らなかった。
♯19 wrote:2011/05/08
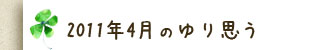
引退。
♯18 wrote:2011/04/19
逆向きのアンテナ。
♯17 wrote:2011/04/17
2011年、夏。奇跡の夜型都市、東京。
♯16 wrote:2011/04/10
故郷の町、電波時計の怪。
♯15 wrote:2011/04/04
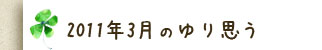
緊急対策の先にあるもの。
~ピンチをチャンスに変える、復興のビジョン~
(ゆりコラム番外編)
♯14 wrote:2011/03/24
いま、なぜ、トラベルミン?
♯13 wrote:2011/03/22
プールに水を溜める。(福島原発)
♯12 wrote:2011/03/20
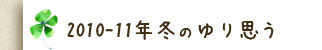
穴あけちゃった!
♯11 wrote:2011/02/22
『ER』に追いついた!
♯10 wrote:2011/01/25
ノン-ノンストップ新幹線。
♯9 wrote:2011/01/05
耳はイヤ~!で、目はアイズ。
♯8 wrote:2010/12/13

未練はない、ゴー!
♯7 wrote::2010/10/31
忘れんぼクイーン。
♯6 wrote::2010/10/24
ごめんくだシャイ。
♯5 wrote:2010/10/16
鰐とおばあちゃん。
♯4 wrote:2010/10/04
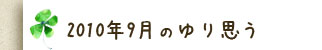
悪女の深情け。
♯3 wrote::2010/09/27
いちばん好きなコンセプト。
♯2 wrote:2010/09/21
中学生向けのコピーで、満足ですか。
♯1 wrote:2010/09/13



